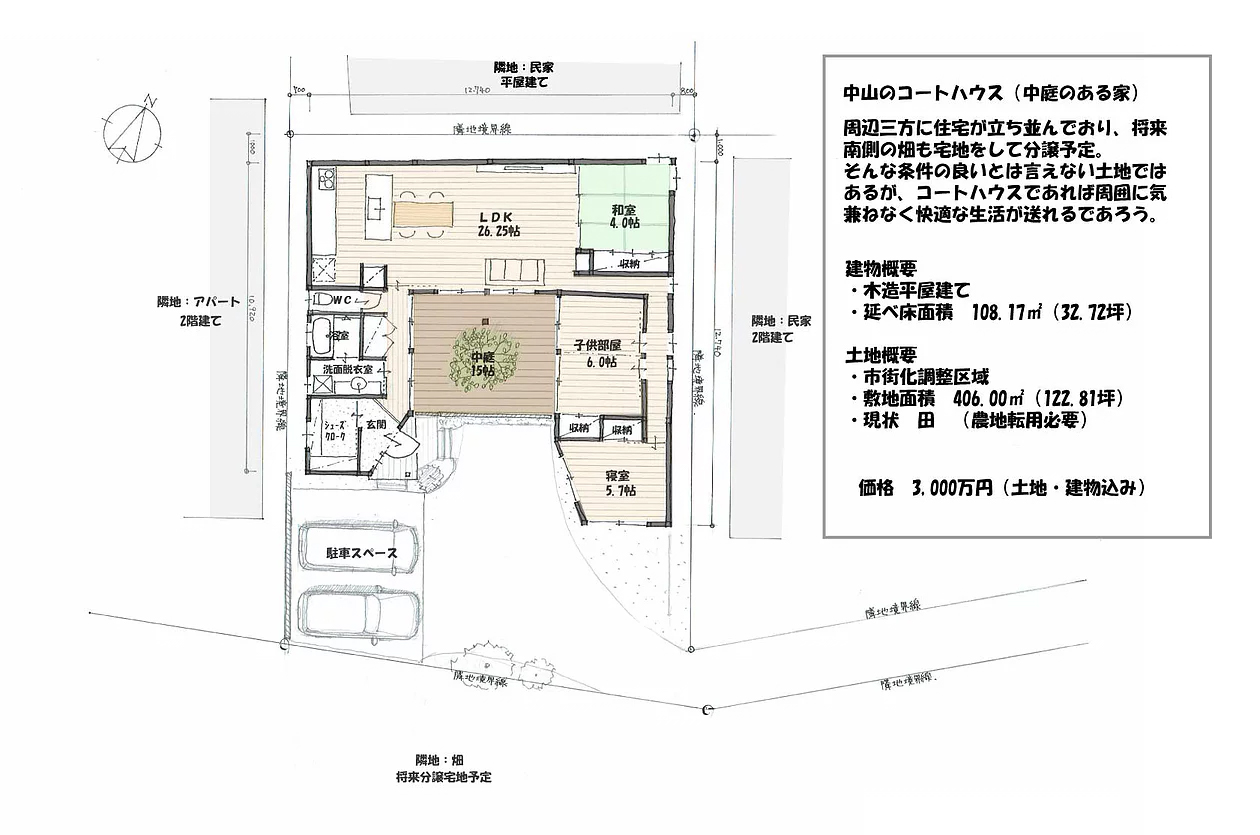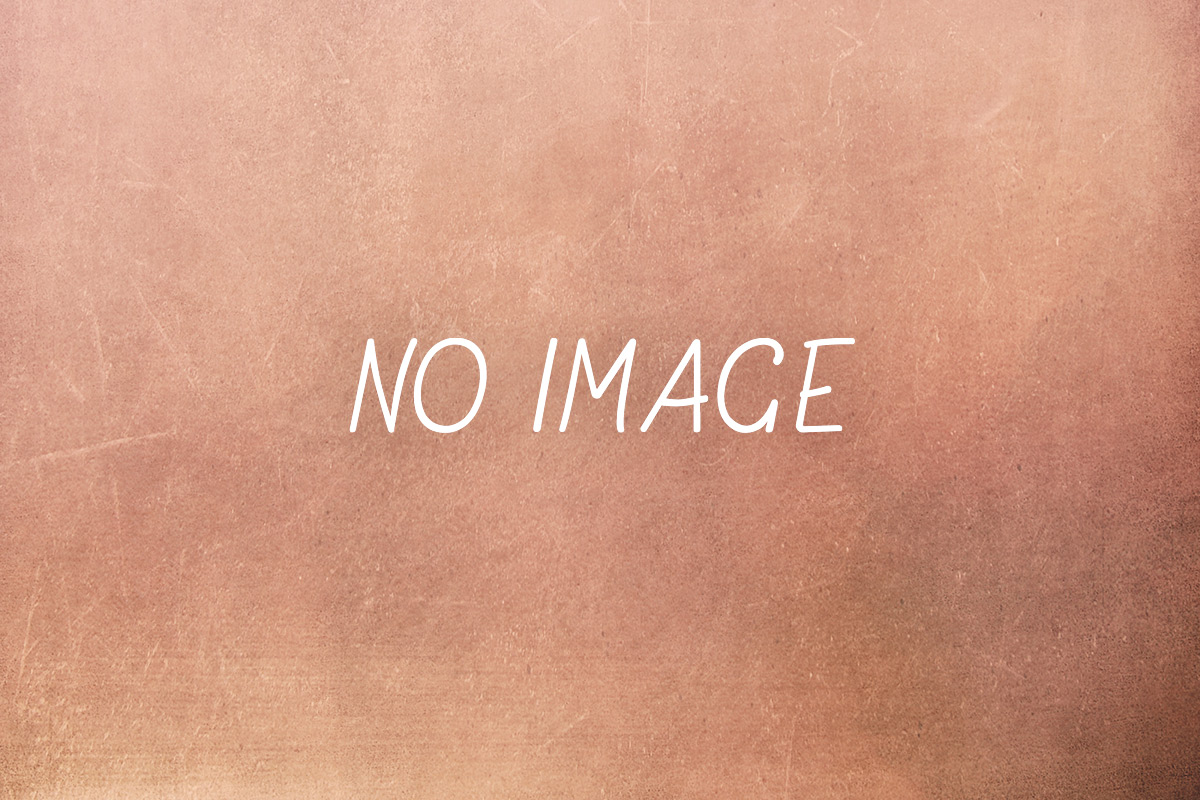「インスペクション」とは「診断」の事。「住宅インスペクション」とは「住宅診断」という意味です。
これまで日本においては、木造の住宅は国税庁の減価償却より22年で価値がなくなるというものでした。
なぜ22年か?と言えれれば、法律制定時の建物はその程度のもの!!!と国が言ってるのと同じです。
しかし近年、ZEHや長期優良住宅、低炭素型住宅などの様に、性能の良い建物を長く使いましょうという方向に国の政策が進んできております。
2020年には、新築物件の断熱性能にも法的チェックがかかってきます。
そうなると木造住宅の減価償却(住宅寿命)の考え方もこれから変わってくるでしょう。
そして、そうなった場合今度大事になることは、性能の良い住宅をいかに維持管理していくか?ということになります。
建物も人間と同じく、健康診断や、時には病院に行かないといけない事はあるでしょう。
特に、住宅の売却を考えている時は、特に重要になってきます。
インスペクションではこれまでの維持管理や改修・修理履歴等も含め、住宅の健康診断を行います。
実はその結果によって、不動産流通センター『価格査定マニュアル』により建物の価値が上がることも多くなってきています。
先日、インスペクションを行った物件においては築35年の木造住宅でしたが、440万の建物の価値があると査定できました。
今後、インスペクションを通じ、建物の維持管理及び売却時の価格判定基準がより明確にスムーズになっていくでしょう。
【点検内容の一例】
●外壁に構造躯体に影響のあるヒビが無いか

●基礎に構造躯体に影響のあるヒビが無いか

●床下の木材に腐食はないか、シロアリはいないか。