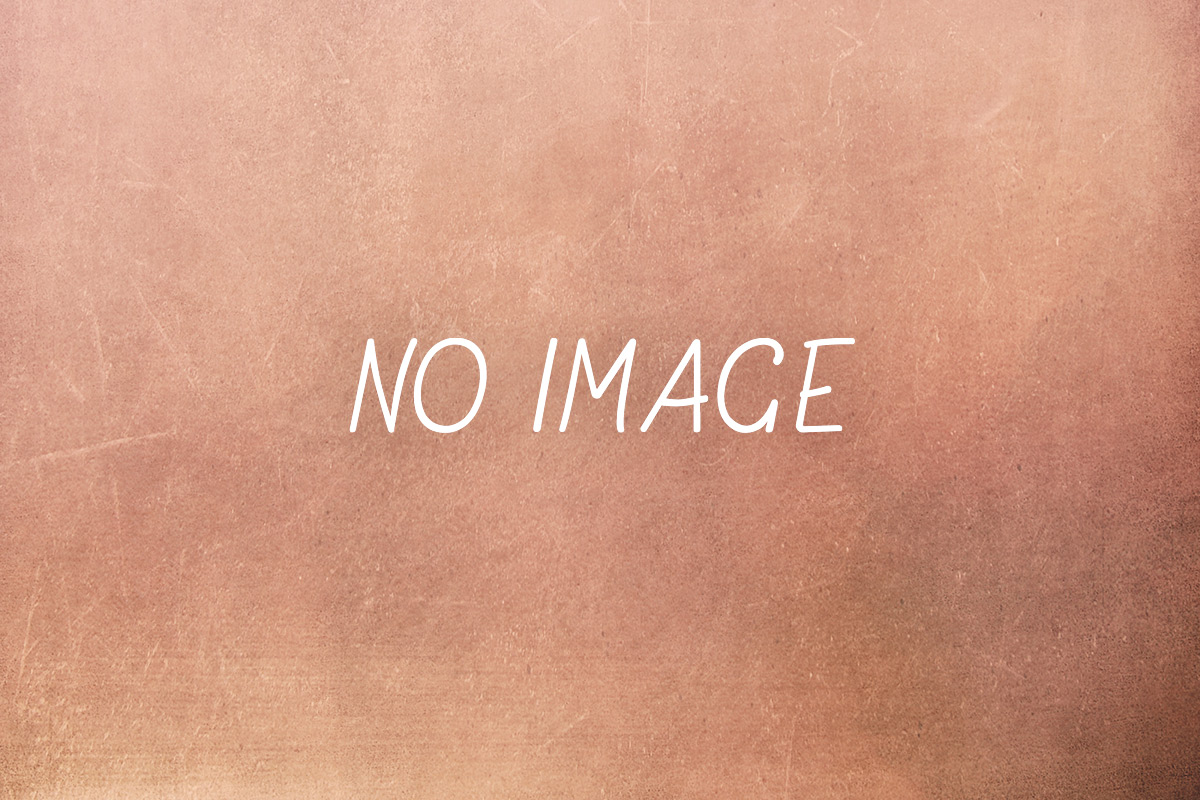
昨日25日土曜日に宮崎にて、九州の建築士が集う 九州ブロック研究集会『建築士の集い』宮崎大会がありました。
私は初めて参加させて頂きました。今年から建築士会青年部の幹事をさせて頂く事なったこともあり、前夜祭や九州ブロックの青年部会議にも参加させて頂きました!
前夜祭は総勢70名ほど!! 九州の建築士が集まり多いに盛り上がりました。
特に驚いたのが大会の主催者側の方々が、このイベントをとても楽しんでいる事!
しかも飲み過ぎ?盛り上げ過ぎ?なくらい(^^;;
そして、当日
まず、午前中に九州ブロックの青年部にて会議。
今後の活動の事など。
そしていよいよ、午後から、
木ん未来 キンミライ 開催
大会という名前の通り、メインは地域実践活動発表を各県が行い、一番を決めるというもの。
今回は震災もあった為、その前に熊本の現状報告もありました。
その後、分科会。講演会やディスカッションなど興味があるものに分かれる。
私は初参加だったので、取り敢えず講演会を。
と言っても、なかなか一度に聞くことがない様な豪華メンバー。
とくに 建築家 内藤 廣 氏 (東大名誉教授)
テーマはもちろん 木 について
内藤先生も宮崎で木を活かした建築を設計しており、その日向駅の設計ウラ話など、面白かった。
腰原 幹雄 氏は現在東大教授、大規模木造建築の構造設計の第一人者。しかし、建築論についてもかなり厳し意見を持つ。
ゲストスピーカーも凄い。
プロダクトデザイナーの若杉 浩一 氏
レモン設計室 河野 秀親 氏
河野氏 は 宮崎在住の宮崎や鹿児島にとても良い建物を創る建築家。
有明町の『蓮の郷』など魅力あり建築をつくる。
トークセッションでは、
なぜ、木を使うか?
木を見せる魅力はなにか?
木造でもいい、予算上、木造しかないをしない!
なんとなく木造をしない!
林業との関わりは?
林業と建築が繋がり合うのが当たり前でないか?国交省と林野庁
木造は文化なのか産業なのか?
近代建築では木造建築は評価されていないが、なぜか?今後は?
瓦屋根木造の本当の設計を知る
と書ききれないくらいの深い建築論議が繰り広げられた。
その後、大会は終了となり、会場を移動し、懇親会へと移った。
正式な人数は分からないが、300人以上は来ていただろう。その一部は前日から、当日もほとんどが、懇親会を楽しんだあと、二次会へと宮崎の繁華街へと繰り出した。
経済的な効果も多く、各県のPRにもなる大変面白い集いだった。
そしてなにより、同業者の集まりなのにこんなにも楽しく真剣に活動する事。
社団法人等の活動にこれまであまり、理解をしていなかったが、今回得るものがかなり大きかった。
